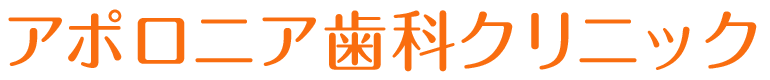インビザラインは、透明なマウスピースを段階的に交換することで歯を少しずつ移動させる矯正治療です。
しかし、どのような仕組みで歯が動くのか、他の矯正方法との違いが気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、歯列矯正における歯の動きの仕組みを解説しながら、インビザライン治療の前期・中期・後期それぞれの段階で、どのように歯が動くのかを詳しくご紹介します。
インビザラインの効果を最大限に引き出すための補助装置についても解説しているので、治療を検討している方はぜひ参考にしてください。
インビザラインとは
インビザラインとは、透明なマウスピースを使用して歯を少しずつ動かす歯列矯正の方法です。従来のワイヤー矯正とは異なり、目立ちにくく、取り外しが可能なため、食事や歯磨きがしやすいのが特徴です。
治療では、歯科医師がデジタルシミュレーションを用いて治療計画を立て、それに基づいてオーダーメイドのマウスピースを作成します。
患者様は7〜10日ごとに新しいマウスピースに交換しながら、徐々に歯を理想的な位置へ移動させていきます。
また、ワイヤー矯正に比べて痛みが少なく、金属アレルギーの心配がないのもメリットの一つです。適応できる症例が広がっているため、歯並びに悩む多くの方に選ばれています。
インビザラインで歯が動く仕組み
ワイヤー矯正との違い
ワイヤー矯正は、歯にブラケットを装着し、ワイヤーの力を利用して歯を動かす矯正方法です。ワイヤーの調整により、歯にかかる力を変化させながら、適切な方向へ誘導します。
ワイヤー矯正の強みは、比較的強い力をかけることができるため、歯のねじれや大きな移動が必要なケースにも対応しやすい点です。
しかし、ブラケットとワイヤーが口腔内に常に固定されているため、口内炎ができやすく、食事や歯磨きがしにくいといったデメリットもあります。
インビザラインは、透明なマウスピース(アライナー)を装着し、段階的に交換することで少しずつ歯を動かす矯正方法です。
1枚のマウスピースで移動できる歯の距離は約0.25mmとされており、弱い力を持続的にかけながら歯を動かしていくのが特徴です。
マウスピースは、治療計画に基づいて設計され、決められた順番で交換することで、歯が計画通りの位置へ移動します。
さらに、歯に小さな突起(アタッチメント)を装着することで、回転や前後の移動といった複雑な動きにも対応できます。
インビザラインは、ワイヤー矯正と比べて痛みが少なく、見た目が目立ちにくいのがメリットですが、大きく歯を移動させる必要がある場合や、噛み合わせの調整が複雑なケースでは、ワイヤー矯正の方が適していることもあるため、症例によって適切な方法を選ぶことが大切です。
歯が動く仕組みは、ワイヤー矯正もインビザラインも基本的には同じです。歯は歯根膜という膜を介して骨の中に埋まっており、矯正装置によってこの歯根膜に一定の圧力が加わると、歯の周囲の骨が吸収され、反対側では新しい骨が形成されます。
この、骨の吸収と形成が繰り返されることで歯が移動します。
ワイヤー矯正は、強い力を断続的にかけるため、初期の歯の移動時に強い痛みを感じることが多いですが、インビザラインは弱い力を持続的にかけるため、痛みが少ないという違いがあります。
また、ワイヤー矯正は定期的な調整が必要なのに対し、インビザラインは患者自身が計画に沿ってマウスピースを交換するため、通院頻度を抑えられるのも特徴です。
インビザラインでアタッチメントを用いて歯を動かす仕組み
インビザライン治療では、歯をより正確に動かすために「アタッチメント」と呼ばれる小さな突起を歯の表面に装着することがあります。
アタッチメントは、歯とマウスピースの密着度を高め、移動の方向をコントロールする役割を果たします。
アタッチメントは歯と同じ色のレジン(歯科用プラスチック)で作られ、治療計画に基づいて適切な位置に設置されます。
通常のマウスピースのみでは難しい、歯の回転・前後の移動・引き上げる動きなどを補助するため、症例によっては非常に重要な役割を担います。
特に、ねじれた歯や歯の根元から動かす必要がある場合は、アタッチメントが有効です。
また、アタッチメントをつけることでマウスピースのフィットもよくなりエラーが起きにくくなる効果もあります。
治療が完了すると、歯科医師がアタッチメントを除去し、歯の表面を元の状態に戻すため、見た目への影響も最小限に抑えられます。
設置や除去は比較的簡単に行えるので、ライフスタイルやイベントの関係でつけたくない部位や期間がある場合も対応可能です。
インビザラインでゴム掛けを用いて歯を動かす仕組み
インビザライン治療では、「ゴム掛け(顎間ゴム)」と呼ばれる補助装置を使用し、噛み合わせや歯の移動を調整することがあります。
ゴム掛けは、小さなゴムをマウスピースに取り付けられたフックやボタンに引っ掛け、歯を特定の方向へ引っ張ることで、適切な噛み合わせを作るために使用されます。
ゴム掛けには、様々な種類があり、上下の歯のズレを改善したり、歯や顎の前後の移動をサポートするために使用されることが多いです。
最終仕上げとして緊密に噛ませたい部位にかけることもあります。
ゴムかけは全て患者様ご自身で行っていただく必要があります。
マウスピースを外すタイミングでゴムもはずし、マウスピースを装着するタイミングでまたゴムをかけていただきます。
ゴムの力を安定して作用させるためには、マウスピースと同じく、決められた時間装着し、ゴムを適切に交換することが重要です。
ゴム掛けを正しく使用することで、治療計画通りに歯を動かし、より精密な仕上がりに導くことが可能になります。
インビザラインで歯が動く段階とは
初期
インビザライン治療の初期段階では、歯を動かしやすい環境を整えていきます。
インビザライン治療が始まるとマウスピースの装着が開始されます。それとほぼ同時期にIPR(歯の隙間を作る処置)やアタッチメントの装着が行われることが多く、治療計画に沿った歯の動きをサポートする準備をします。
抜歯が必要な治療計画の場合は抜歯もこのタイミングで行われることが多いでしょう。
マウスピースを装着して、歯に少しずつ力をかけて動かし始めますがこの段階では、まだ大きな変化は感じられません。
マウスピースを適切に使用することに慣れて歯が動きやすい環境を整えることが大切です。
中期
中期に入ると、本格的に歯が移動し、見た目の変化を実感しやすくなる段階です。この期間は、歯の並びを整えながら、噛み合わせの調整も並行して行われます。
ゴム掛け(顎間ゴム)もこの段階からスタートすることが多く、適切に使用できるかどうかは仕上がりに大きく関わっており、この段階での顎間ゴムは歯や顎を適切な位置に誘導していく目的で使用されることが多いです。
また、中期の段階では、歯の動きに応じて新しいマウスピース(追加アライナー)を作成することもあります(リファインメント)。
これは、治療計画通りに歯が動いていない場合や、より精密な調整が必要な場合に行われる追加のマウスピースです。
どんなにしっかりと治療計画を立てても、人の歯が100%コンピュータ通りに動くことはありません。
この過程を何度か繰り返すことで、より理想的なゴールへと近づけることができます。
一番大切なことは何よりも、マウスピースの装着時間を厳守することです。1日22時間以上適切に装着することで、治療の進行はスムーズになります。
後期
治療の後期では、歯並びの仕上げを行い、最終的な噛み合わせの調整が進められます。
この段階では、細かな噛み合わせのズレを改善し、歯が後戻りしないように安定させることが目的です。噛み合わせの微調整のために顎間ゴムが使用されることもあります。
後期では、歯の細かい角度や噛み合わせのバランスを整えます。場合によっては、一部のアタッチメントを除去し、最終的な歯の位置に合わせた仕上げの調整が行われることもあります。
歯の位置がゴールに達成したら、全てのアタッチメントを除去してリテーナー(保定装置)を作製します。
リテーナーの使用は非常に大切です。矯正が完了しても、歯は元の位置に戻ろうとするため、リテーナーを一定期間使用し、歯並びを安定させる必要があります。
リテーナーは、最初の数か月は長時間装着し、徐々に装着時間を減らしていくことが推奨されます。
インビザラインの矯正期間はどれくらい?
インビザラインの矯正期間は、症例の難易度や歯の移動量によって異なります。
軽度の歯並びの乱れ(部分矯正)であれば6か月〜1年程度、中等度以上の全体矯正では1年半〜3年程度かかることが多いです。
特に、抜歯を伴うケースや奥歯の噛み合わせの調整が必要な場合は、治療期間が長くなる傾向にあります。
また、矯正終了後は後戻りを防ぐために「リテーナー(保定装置)」を装着する期間が必要です。
治療を出来るだけ早く終わらせるためには、1日22時間以上の装着を守り、歯科医師の指示通りにマウスピースを交換すること、定期的な通院でのチェックを欠かさないこと、が重要です。
インビザラインに適している歯並びの症例
インビザラインに適している歯並びの症例
インビザラインは、軽度〜中等度の歯列不正に適しており、比較的歯の移動量が少ないケースが得意と言われています。
しかし近年ではインビザラインシステムの目覚ましい進化により、かなり複雑な症例にも対応できるようになっています。
具体的には、以下のような症例に適応可能です。
- ・軽度〜中等度の叢生(歯のガタつき)
- ・すきっ歯(空隙歯列)
- ・軽度の出っ歯(上顎前突)
- ・軽度の受け口(下顎前突)
- ・軽度の噛み合わせのズレ(交叉咬合・開咬)
インビザラインに適していない症例
歯の移動量が大きい症例や、骨格の問題を伴う場合は、インビザライン単独では対応が難しいことがあります。
以下のようなケースでは、ワイヤー矯正や外科矯正が推奨されることもあります。また、インビザライン矯正の一部でワイヤーを使用するという方法もあります。
- ・重度の叢生(歯のガタつきが大きい)
- ・歯の回転量が大きい
- ・埋伏している歯がある
- ・重度の出っ歯や受け口(骨格的な問題がある)
- ・極端な開咬(奥歯だけ噛んでいる状態)
インビザライン矯正を検討している方は、高知市の「アポロニア歯科クリニック」へご相談ください
高知市の「アポロニア歯科クリニック」では、インビザラインでの矯正治療を提供し、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案しています。
「自分の歯並びがインビザラインで治療できるのか知りたい」「矯正期間や費用について詳しく聞きたい」など、矯正に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
経験豊富な歯科医師が丁寧にカウンセリングし、最適な治療計画をサポートします。
ご予約やお問い合わせは、Webから受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。